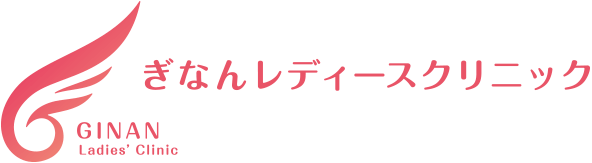8月に名古屋市で行われた日本受精着床学会に胚培養士3名が参加しました。
今回の学会では、最近話題になっている「胚培養士の資格制度」についてのシンポジウムがありました。
ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、胚培養士には国家資格がなく、学会認定資格制度はありますが、公的な能力認定や保護などはありません(もちろん、実際の培養業務は十分な経験があるか、十分にトレーニングを積んだ胚培養士だけが行っています)。
現状としては、胚培養士養成コースがある大学(岐阜県内では、岐阜医療科学大学に胚培養士養成コースがあります)がいくつかある、という状況ですが、それらの充実が国家資格化への道筋になると考えられます。
今回のシンポジウムで非常に印象深かったのは、放送局の記者の方の発表で「当事者の声」として、患者さんたちからの胚培養士に関するご意見を聴かせていただけたことでした。
中でも、「私たちは胚培養士というものをそもそも知らない。どんな技術を持っているのかも知らない。認知度を上げる試みや、胚培養士に関する情報提供は必要では。そもそもどうやったら胚培養士の情報が入手できるのかさえわからない」といった声には衝撃を受けました。
当院では胚培養士による培養結果説明や、専門の資格を持ったスタッフによるカウンセリングを行っています。
卵子や精子、胚についてわからないことがある場合は、気軽にお声をかけていただければ、と思っています。